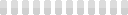著者・出版社・関連アーティスト
商品説明
本土空襲に備え、昭和12(1937)年に成立した防空法を中心とする「民防空政策」。焼夷弾火災に対する「敢闘精神とバケツリレー」に象徴される防空法は、国民に負担を強いるだけの悪法のように論じられてきた。しかし、防空法は、「監視、通信、警報、燈火管制、分散疎開、転換、偽装、消防、防火、防弾、防毒、避難、救護、防疫、非常用物資の配給、応急復旧」という空襲の流れを網羅し、準備から空襲後の処置・復旧にまで対処するように定められている。消防・防火の失敗だけで評価することが本当に妥当なのか?本書では、防空法を中心とした民防空の国民保護政策としての歴史的意義を検証し、今日の防災へと繋がる「教訓」を明らかにする。
関連記事
収録内容
| 1 | 第1部 研究の進め方(問題の所在 |
| 2 | 先行研究 |
| 3 | 研究の必要性 |
| 4 | 防空法とはどんな法律だったのか |
| 5 | 研究の進め方 |
| 6 | 用語の整理など) |
| 7 | 第2部 空襲への準備(「組織・訓練」 |
| 8 | 「空襲判断」 |
| 9 | 事前の防御措置) |
| 10 | 第3部 空襲時の対処(「監視」「通信」「警報」 |
| 11 | 「燈火管制」 |
| 12 | 「偽装」 |
| 13 | 「消防・防火」) |
| 14 | 第4部 空襲後の処置(「応急復旧」 |
| 15 | 空襲に際する防衛対策(「防毒」「防疫」「応急復旧」「給水」「清掃」) |
| 16 | 防空法の災害対処(「救護」「非常用物資の配給」「応急復旧」)) |
| 17 | 第5部 民防空政策と国民保護 |