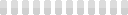著者・出版社・関連アーティスト
商品説明
理想と現実の間で苦悩する地域のラジオ局。ネット時代に入り、改めて注目を集めるコミュニティ放送。制度化され25年、全国調査からその厳しい現実が見えてきた。巨大スポンサーも受信料もなく、地方再生に挑む小さなラジオがどのような役割を果たし、地域をどう変えるのか。多様な視点と事例研究から研究者たちが新しい「公共」放送への提言を送る。
関連記事
収録内容
| 1 | 第1部 コミュニティ放送に迫られているもの(制度的プレッシャーの視座からみる防災の役割 |
| 2 | 全国調査の結果から―コミュニティ放送はこうして放送されてきた |
| 3 | コミュニティ放送にジャーナリズムは必要か |
| 4 | 新たなる資源調達―多様な分産財源を目指して |
| 5 | 指標調査から見たコミュニティ放送における公共性の論点) |
| 6 | 第2部 日本のコミュニティ放送の多様性(放送局の担い手の誕生―おおさきエフエム放送の事例から |
| 7 | 沖縄でソーシャルワーク機能を果たすコミュニティFM |
| 8 | 奄美群島のコミュニティラジオの文化装置的役割 |
| 9 | 大学が関わるコミュニティ放送) |
| 10 | 第3部 問い直されるコミュニティ放送(放送と地域コミュニティをつなぐ仕組みを作る―番組審議会のリ・デザイン |
| 11 | コミュニティ放送局はいかに調べられ、語られているか―3.11後の研究動向 |
| 12 | パーソナル・マス・コミュニケーション時代のコミュニティ放送―現われの空間として) |
| 13 | 第4部 基幹放送への問いかけ―持続可能な放送のために(日本の放送行政、とくに基幹放送のあり方に問いかける |
| 14 | 伝送路のこだわりを越えてオンライン放送局になったFMわぃわぃ) |
| 15 | 資料 |